このコラムの監修者
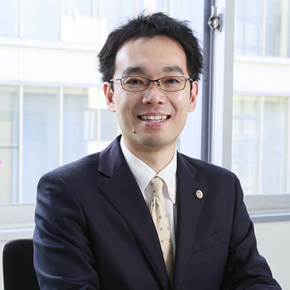
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
「長年そのままになっている借金は、時効だから返さなくてもいい」
そういう話を、聞いたことがあるのではないでしょうか。
「借金の消滅時効」
という言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。
債務整理のご相談でお越し頂く方の中には、たとえば次のようなケースもあります。
「大手消費者金融からの借金を返さなくなり、連絡があっても無視していた。長年そのままになっていたが、最近になって突然、債権を譲り受けたという債権回収会社から督促状が届いた・・・」
消滅時効で借金が消えるというのは、珍しいケースではありません。
上場企業の大手金融業者、あるいはクレジットカード会社からの借入れであっても、消滅時効で借金が消える可能性は十分あります。
消滅時効が成立すれば、借金を返済することなく、借金問題を解決できる場合もあるのです。
もっとも、きちんとした手順を踏む必要があります。
「時間の経過で自動的に借金が消滅する」ことはありませんし、消滅時効を主張できなくなる場合もあります。
今回は、借金を消すことができる、「消滅時効」という制度について解説します。
時効には、「取得時効」と「消滅時効」という2種類があります。
借金問題解決に役立つのは、このうち「消滅時効」という制度です。
消滅時効とは、法律で定められた一定の期間、権利を行使しなかったことによって、その権利が消滅してしまうという制度です。
なぜこのような制度があるのかという理由はいくつかあります。
その1つは「長年、権利を行使しない者は、法律上保護する必要がない。むしろ長年続いたその事実状態を尊重すべきである」というものです。
借金問題において、消滅時効を主張してこれが認められると、貸金という債権(貸主の財産)が消えてなくなることになります。
借主の側から言えば、借金が消えるので返す必要もなくなるというわけです。
では、具体的に、どのような状態になれば、消滅時効を利用できる状態といえるのでしょうか。
民法の時効の制度については、民法改正によって、それまでの内容と変化しています。
まず、現在施行されている改正後民法での消滅時効の定めは、このようになっています。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2(以下省略)
債権というのは、お金の貸し借りに関していえば、「お金を返してもらう権利」のことです。
「債権者が権利を行使することができる」とは、借金を返してもらえる状態のことをいいますから、支払期日が到来したときのことをいいます。
お金を貸すときは、当事者間でいつまでに返すという取り決めをしたうえで貸し借りをするのが一般的です。
ですので、貸主は、支払期日の到来と同時に、権利行使できることを知っているといえるでしょう。
そのため、民法第166条1項1号が適用され、支払期日から5年で、消滅時効にかかることになります。
改正前民法では、債権の消滅時効は、原則として10年と定められていました。
つまり、お金の貸し借りについていえば、民法の改正によって、時効の期間は短くなっています。
では、旧民法と新民法のどちらが適用されるかは、どのように決まるのでしょうか。
基本的には、お金を借りた時期が、新民法の施行日である令和2年4月1日以降であれば新民法が、それより前であれば旧民法が適用されることになります。
そのため、令和2年4月1日以降の借入れについては5年、それより前の借入れについては10年の時効期間が適用されます。
もっとも実際上は、令和2年4月1日より前の借入れでもほとんどの場合は、借り入れ先は銀行、クレジットカード会社、消費者金融といった会社であろうと思われます。
このような会社からの借金については、商事時効が適用されて時効期間は5年となりますので、結果的には民法改正の前後で変わりはありません。
(ちなみに商事時効の制度は、民法改正とともに廃止されています)
たとえば次のような場合があります。
もう時効だと思っていたが、必要な期間が過ぎていなかったという場合です。
「判決を取得されており、時効期間が10年に伸びていた」
というのがその典型例です。
もっとも、実際に法律相談を受けていると、「そもそも判決があったかどうかも全く分からない」という方も少なくはありません。
しかし、判決を取られたかどうかといったことを、借入先に自分で確認するのは大きなリスクを伴います。
借入先にうかつに接触する前に、弁護士に相談することをお勧めします(詳しくは後述します)。
時効期間満了前に債務承認をすると、その時から新たに時効が進行します。
たとえば支払を猶予してほしいとか、借金を分割払いで支払っているというのは、債務承認にあたります。
ちなみに時効期間満了後に債務承認をした場合も、以後時効を援用できなくなってしまいます。
(新たに時効期間が満了すれば別ですが。援用については次項参照)
消滅時効は、「法定の期間が経過したら、そのまま放っておけば借金が消えている」というわけではありません。
消滅時効による利益を受けるためには、消滅時効で利益を受ける人(=端的にいえば、借金消滅という利益を受ける借主)による、時効の利益を受けようとする意思表示が必要です。
このような意思表示を、時効の「援用」といいます。
消滅時効の援用をしない限り、時間が経っただけで借金が自動的に消滅するということはありません。
単に「借入先が督促してこない状態が続いている」というだけで、借金は残り続けたままなのです。
しかも、支払がずっと遅れているわけですから、遅延損害金が日々どんどん増えていくことになります。
消滅時効について自力で色々調べてみたのでしょうか、
「自分も消滅時効になっていないか知りたい」
「判決を取られていないかどうか知りたい」
ということで、自分自身で借入先に接触する方がいます。
しかし、それはお勧めしません。
借入先の担当者はいわば回収の専門家です(前述のとおり、銀行などから借りている方がほとんどですから)
借主が接触してきたのをこれ幸いと、債務を承認する方向に誘導させられてしまうことがあります。
そうなると、「せっかく時効期間が満了していたのに、債務承認させられた結果、消滅時効が認められなくなってしまった」という話になりかねません。
実際、当事務所に依頼頂いた方の中には、「過去に自分で時効援用をしてみたが、失敗して全額払わされ痛い目を見た。なので今回は依頼したい」という方もいらっしゃいました。
「債権譲渡を受けた債権回収会社から自宅訪問の予告をされている」
「(貸主側の)弁護士から通知が来ている」
そんな状況なのに自力で対応するというのは、精神的にも負担が大きいです。
消滅時効の援用を弁護士に依頼すれば、弁護士が受任通知(=仕事の依頼を受けたという通知)を貸主に送ります。
すると、貸主側からの事実上の取立て(=電話、督促状送付、自宅訪問など)を止めることができます。
そうなると、取立てのプレッシャーや精神的負担などを免れたうえで、消滅時効援用の手続きを確実に進めていくことができるわけです。
消滅時効の援用は、成功すれば有利に借金問題を解決できる可能性があります。
場合によっては一挙に借金問題が解決できるかもしれません。
しかし他方で、時効の手続きのやり方を誤ると、時効だと認められなくなってしまうことがあります。
長年返していない借金がある方は、借入先に接触する前に、まずは一度弁護士にご相談ください。
このコラムの監修者
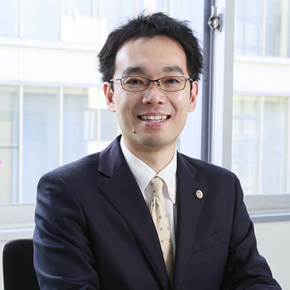
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
1 時効期間満了後に支払督促を取られたら? 「借金を2009年からずっと払っていなかった。2019年に支払督促が簡易裁判所から届いたが、異議申立てをせず放っておいた。そのため、支払督促が確定...

はじめに 任意整理をして分割払いの示談をすると、おおむね36回=3年程度の長期間をかけて支払っていくことになります。 任意整理で示談がまとまっても、完済するまでには長期間かかりますので、その...
