このコラムの監修者
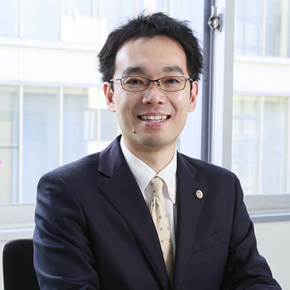
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
「借金を2009年からずっと払っていなかった。2019年に支払督促が簡易裁判所から届いたが、異議申立てをせず放っておいた。そのため、支払督促が確定してしまっていた」
このように、借金の時効期間(多くの場合5年)が満了した後に、支払督促が申立てられて確定済みの場合があります。
支払督促確定後に時効を主張することはできるのでしょうか。「支払督促確定前の段階ですでに借金は時効だった。だから借金を支払う必要はないし、その支払督促で強制執行をすることも許されない」と言って争うことはできるのでしょうか?
結論からいうと、支払督促確定後に時効を主張して、強制執行は許されないと主張することはできます。実際、当事務所が交渉した結果、貸金業者に時効を認めさせ、その支払督促で強制執行はしないと約束させたことも何度かあります。
しかし、時効を認めてこない業者もあります。こちらから業者に対して訴訟を提起して、争っていかなければならない場合もあるのです。
(備考)時効期間満了前(5年が過ぎる前)に支払督促がなされ権利が確定すると、時効の更新事由となるため時効期間のカウントが振り出しに戻ることになります(民法147条)。
支払督促とは、ごく簡単に言えば、簡易裁判所の書記官という人から請求書が送られてくる手続きです(民事訴訟法382条以下)
支払督促と業者が直接送ってくる請求書(ハガキ、手紙)とでは、違う点があります。支払督促の手続きが一定段階を超えると(仮執行宣言がつくと)、給与差し押さえなどの強制執行が可能になる点です。
もし業者が、自分が送った請求書を無視されたとしても、いきなり強制執行することはできません。しかし、簡易裁判所書記官を通じて送った支払督促が無視された場合には、仮執行宣言がついた後には強制執行ができるようになるのです。
支払督促が手元に届くと(送達されると)、そこには注意書や督促異議申立書が一緒に同封されていることがあります。注意書には、次のようなことが書かれているかと思います。
(備考2)東京簡易裁判所でいえば、支払督促を担当している民事7室は墨田庁舎にありますが、通常の裁判に移行すると、霞ヶ関で裁判をすることになります。
支払督促に対して督促異議を申立てないと、債権者の申立てにより仮執行宣言がつけられます。仮執行宣言がつくと、強制執行される可能性が出てきます。
(備考3)仮執行宣言がついた後でも、2週間以内なら督促異議申立てができます(民事訴訟法393条)。しかし、支払督促の効力は失われません。その異議申立てだけで強制執行を止めることもできません。
支払督促に仮執行宣言がついて2週間を過ぎると、もはや督促異議を申立てることはできません。支払督促が確定したことになります。「その支払督促で強制執行できる」という状態が確定することになります。
支払督促確定というのは、その支払督促で強制執行できることが確実になったという意味です。しかし、「支払督促で請求されている借金が存在していることが確定した」というわけではありません。支払督促確定は、借金存在のお墨付きではないのです。
この点、法律上、支払督促は「確定判決と同一の効力」を有するとされています(民事訴訟法396条)。
しかし、確定判決と確定した支払督促とが、全く同じように扱われるわけではありません。
判決は、裁判官が、双方の言い分を聞き、公平な裁判をして出すものです。裁判官は、たとえば「時効になっている」というような言い分を聞いたうえで判決を下すのです。
敗訴判決に控訴せず確定したら、「借金(判決記載の請求権)が存在していることが確定された」ということになります。
(備考4)訴訟の口頭弁論に呼び出されたということは、時効の言い分を述べる機会を与えられたことになります。機会を与えられたにもかかわらず時効主張をせず判決が確定した場合、後から時効主張はできません。ただし判決確定から10年が過ぎれば、時効主張は可能です。
支払督促は、簡易裁判所書記官が、債権者の言い分のみを聞いて出すものにすぎません。裁判官が双方の言い分を聞いた上で出した結論ではありませんので、「借金が存在している」と確定するわけではありません。
支払督促確定というのは、借金が存在しているというお墨付きではありません。したがって、借金の存在を争えることになります。「支払督促確定前に既に時効になっていたと反論できる(=支払督促確定後でも時効援用できる)」という理屈になります。
支払督促確定後に時効援用したとして、業者が借金の時効を認めてくる場合と、認めてこない場合があります。
業者が借金の時効を認めるということは、その借金を請求しないということです。
業者は、確定済み支払督促があるので、強制執行をしようと思えばできる状態です。しかし時効を認める以上、請求も強制執行もしてこないことになります。
したがって、請求異議訴訟(後述)を提起してまで争う必要はないのではないかと思われます。業者が自発的に時効を認めておきながら、前言撤回して強制執行してくるという可能性は、事実上ほぼ無いと言って良いでしょう。
業者が借金の時効を認めないということは、請求する意思がある、請求しないとは約束できない、ということです。
業者は、確定済み支払督促があるので、強制執行をしようと思えばできる状態です。そうなると、請求異議訴訟で争っていくことも検討する必要が出てきます(次項参照)
請求異議訴訟とは、「強制執行を許さないと裁判所に宣言してもらう」という訴訟です。
支払督促が確定すると強制執行される可能性が出てきますが、裁判所に、強制執行を許さないと宣言してもらうわけです。支払督促を取られた人が、業者を被告として、裁判を起こすことになります。
請求異議訴訟に勝訴すれば、その支払督促による強制執行は許されなくなります。
請求異議訴訟に敗訴すれば、その支払督促による強制執行を受ける可能性が、残ったままになります。
これまでの裁判例として、請求異議訴訟で勝訴した(=時効を認めてもらえた)裁判例もありますが、敗訴した(=時効を認めてもらえなかった)裁判例もあるようです。法律の規定からすると勝訴するのが自然のようにも思われますが、注意が必要です。
時効期間(多くは5年)が過ぎた後に、支払督促を申立てられて確定してしまっている場合があります。
時効期間満了後に支払督促が確定していても、「支払督促確定前に時効になっていたから支払う必要はないはずだ」といって争うことは可能です。実際、当事務所が交渉して、複数の業者に時効を認めさせたこともあります。
しかし、交渉しても時効を認めない業者もいます。その場合、「こちらから請求異議訴訟を提起して時効を主張する」ことが必要かもしれません。請求異議訴訟で敗訴した裁判例も存在しているようですので、勝訴確実と安心していられるわけではありません。もしこちらが勝訴しても、業者が控訴してくる可能性もなくはありません。
時効期間満了後に支払督促が申立てられ確定していたからといって、借金が時効にならないと諦める必要はありません。しかし、場合によっては、こちらから請求異議訴訟を提起していかなければならないこともある、ということです。
関連記事 時効援用:払わなくていい借金かも
このコラムの監修者
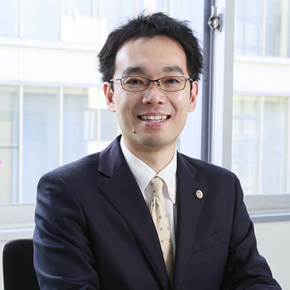
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
はじめに 「自己破産すると家族に影響がありますか?」というご質問をいただくことがあります。家族に影響があるかどうか、あるとしてどこまでの影響があるのかは、ご相談者の置かれている状況によって...

はじめに 「A社の任意整理を希望しますが、それ以外は一切考えていません」 そう言って、A社以外の借入れについては説明しないという方がたまにいらっしゃいます。 弁護士は、A社以外についてご本人...
